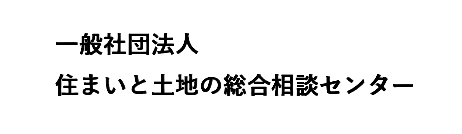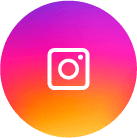BLOG ブログ&コラム
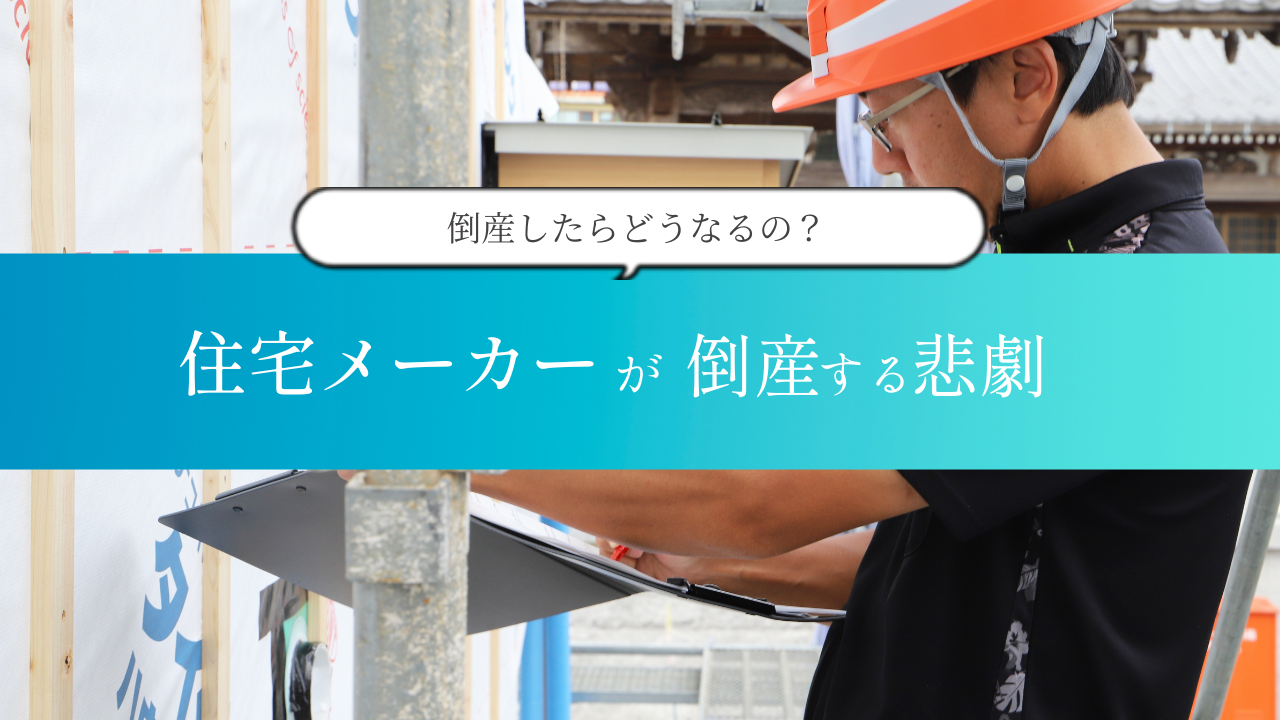
住宅メーカーが倒産する悲劇
住宅メーカーの倒産件数が増えている
東京商工リサーチによると、2024年1~12月の建設業倒産状況は、1924件(前年比13.6%増)に達し、2015年以降の10年間で最多を記録している。ちなみに2023年は1693件(前年比40%超)なので、直近2年でもすさまじい数の建設会社が倒産に追い込まれている。当職の耳にも、工務店が倒産または、倒産の危機に直面しているという話や相談は非常に多く入ってくる。直近だと、新潟市ニコハウスや姫路の企広、三重のやまぜんホームズなど、WEB検索をするとかなりの負債額で倒産しているのがわかる。
悲惨なケースは、着手金(契約金)を数百万払い、工事着工前または着工時に1000~2000万のお金を払い込んだ直後に、会社が倒産するケース。まだ工事が始まっておらず、更地のままで工務店が倒産してしまうと「詐欺だったんじゃないのか!?」「お金を返して欲しい」と、当然思うわけだが、事実上返金されることはほとんどない。

写真は数年この状態の敷地。一度基礎工事完了まで進んだが、基礎を壊してこのまま…。
業界慣習である、いびつな支払いの考え方
誰しもが一軒家を建てよう!と思ったときに、不安視するのは「依頼先の会社が倒産しないか?」という点。特に、大手ハウスメーカー以外のビルダーや、地域の工務店に依頼する場合には、その不安を完全に払しょくできる会社は稀有だと思う。
皆さん勘違いしているのは、かなり大規模だと思っている住宅会社でも基本的に、運転資金は【自転車操業】と言ってよい。
数千万の買い物であり、かつ何もないところから建てるという特異性から、一般的に支払いは【契約時】【着工時】【上棟時(中間金)】【完成時】という形で、分割で支払いを行っていく。こうした分割支払いは、家を建てる期間が長く、材料を購入し工事をしていくなかで全額を住宅会社が負担していくのは、会社からの持ち出しが多く、請負者側の負担が大きいために難しいためとされているし、致し方ないと思う。しかしながら、問題(注意点)は、その分割金額の比率である。
例えば、3000万の家を建築するのに、着手金が300万(10%)・着工金が1200万(40%)・中間時が1200万(40%)・完成時が300万(10%)だとする。これだと工事が始まっていないにも関わらず、半分の1500万を住宅メーカーや工務店に振り込むわけだから、少し考えれば「こんなに必要なの?」と思うはずだが、家を建てたことのない方は「これが普通なのかな・・」と思い(または営業が思わせる)、支払ってしまう。まずは、これがかなりリスキーな支払いサイクルだと認識すべきである。
倒産したらどうなるのか?
工務店が倒産した場合、基本的には社長も一緒に「個人破産」手続きをとるため、お金の取りどころはなくなる。結局、倒産する場合には、会社の負債額は数十億~数百億に上るわけだから、まったくお金がないと言ってもいい。わずかばかりのお金が残っていたとしても、返済の優先順位は「金融機関からの借金」と「従業員や下請けへの未払い」が優先されるので、注文者には返ってこない。これは【建築工事請負契約】が、事実上、双方の債権債務がイーブンに近い、つまり言い換えれば「そこに依頼した人が悪い」という事で、片づけられるためである。
こういったニュースを知っていても「自分には関係がない」「自分たちは注意をしているから大丈夫」と思っている方が非常に多い。悲劇は我が身に迫っているのに、気づかない・注意を払えない理由としては、「地元では有名だから」「街中で現場を見かけるから」「営業マンが誠実だから」「展示場が立派だから」と言った、実はなんのエビデンスもない事象によるものだと思う。
防ぐ手立ては?
こういった危機的状況を回避するためには、下記のことに注意していただきたい。
-
依頼検討している会社の財務状況を確認するように努める
-
その会社で建てたOBの人に、メンテナス実施状況を確認する
-
支払い比率を確認する
-
工務店であれば社長や役員など「経営陣」と一度、面談をする
-
あまりにローコスト・大量受注をしている会社は避ける
一部上場会社では、IRなど閲覧することが可能だし、帝国データバンクや商工リサーチなどから情報取得も可能。非上場でも少なくとも、ここ数年の売上やその年の見込みをヒヤリングし、会社規模と比べて検討をしたい。OBに話を聞くのは、会社が火の車状態の場合、メンテナンス業務の優先度が極端に下がるためである。
そして最もわかりやすいのは「支払い条件」である。前述のような比率を契約書に盛り込んでいる工務店は避けたほうが無難。倒産の可能性が高いと言っても過言ではない。
年間100棟程度以下の、地域の工務店であれば是非とも「経営者」との面談を申し入れるべき。社長でなくてもよいが、実際に会社のかじ取りをしている人と面談をし、これまで、現在、これからの会社ビジョンを聞いて、安心できるかどうかを、判断してもらいたい。
最後に、自転車操業の最たる会社は「ローコスト」で「大量供給」している会社だろう。1棟あたりの利益が少なく、数を売って利益を確保している場合、現代のような不安定な経済状況下だと、売上・利益があっという間にマイナスに向かう。こういった会社と契約する場合には、細心の注意を払ってほしい。
外からみてどんなに好調な会社でも、倒産危機はどうしてもぬぐえない。心配な場合には、【完成保証】が付与される会社を選ぶべきだと思う。
記事作成:市村崇